Lay Your Hands (Pop Mix)
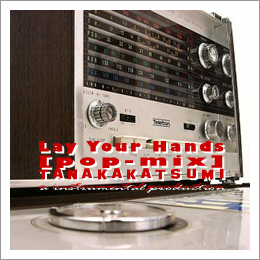
■田中勝己コメント
僕は、曲を書いて誰かに渡す様な、所謂作曲家ではないのです。だから、最終段階まで付き合う必要があって、一曲作るのに結構時間が掛かるのです。
ある人に職業を聞かれ、僕はこう話した。彼はSF(サイエンスフィクション)の好きな人だったらしく「その内、頭に針かなんかの電極を刺せば、音楽なんて聞ける様な世界になるよ。」と、如何に僕が一曲の制作に費やす時間が無駄なのかを述べた。この彼の言葉を借りると、この世に存在する全ての「一人多重録音・宅録ファイナライザー」(特撮物のタイトルみたいですが)な制作者は無駄になる。個人の範疇なら、僕の存在も人生も過程もたちまち無駄という訳だ。
この曲を作り、発表する現在、鑑賞できる音のデジタル容量単位は1/10位に圧縮されはしたが、電極を頭に刺すという鑑賞方法は僕の知る限り存在していない。ましてや基本、重要な要素は全て過程として費やした。つまり、機材は変更があったものの、根本的な部分はキャリアを始めた時から何一つ変わっていない。便宜上「ド」と言う音をキーボードで叩くと、MIDIというプロトコルを介して、設定を変更しない限り別のヴォイスモジュールでも同じ場所の「ド」に指定された音が発音される。その入力された物(ノート)を、単発や連続で指定し(パターンやフレーズ)結果分母と分子で構成される数学的に纏まった物がシーケンスデータになり、ここらへんで作曲からアレンジという工程になり、そのデータをそれぞれ指定された音で発音した物をミキサーに纏め、2ないし6なり、指定したトラックをスピーカ(BUS)に振り分け、(つまりミキシング)出音を纏めた物が「ミックスされた音」ないしは「曲」であり、そのマスタリングの工程を経て、最終結果を耳
にしているのだ。それが「音楽」なのか「雑音」なのか「騒音」なのかは別として。
今回、このオファーを頂いたとき「これをやってみよう」というひらめきと、思いつき。そうでなければ、この曲は出来なかったと思うし、作らなかったと思う。手持ちのMSXやATARIなどの起動音、効果音、ノイズ、本体を叩く音まで、片っ端から0.1秒間のサンプルを取って、ループさせると綺麗に連続した信号音が出ます (Rolandが過去に発表したLA音源やDLM音源と同じ手法ですが。)。それを、MoogやE-mu、SEMなど異なったフィルターに通すだけでも全く違う音になる。
むしろこの作業が楽しくて肝心の曲はと言うと、鳴っている音が曲を作っていく。そういう曲です。世の中のお手本や入門書に記されている作曲手法とは全く違う曲の作り方もあるのです。家に戻るまでが遠足なのと同様、ノイズをひっくるめて、イントロから曲終わりまでが「この曲」なのです。作っている最中、電源が落ちたり、ハードが固まったりしたら、同じ曲が作れるか?ったら、返答に困る様なライヴ感溢れる制作過程です。ちょこまかセーブしてたのでその都度、その時点
には戻れますが…。
念の為、特に頭に針刺して電極で音楽を聞く方法。というか、その環境下での再生を仮定してファイナルミックスしてないので、スピーカーやヘッドフォンでお楽しみ下さい。そんな時代に産まれていて良かったな、と思うのです。頭に電極を刺す事自体痛いと思いますので。
※田中勝己氏には、さらにこの曲についてのあとがきをご執筆いただきました。「何度か聴いた後に読んでいただきたい」というアーティストの意向を踏まえ、Amusement Center会員(登録無料)のみご覧いただけるコンテンツとしてご提供いたしております。あしからずご了承ください。
